<第1回>
東京からさほど遠くない地方都市Т市。終戦の当時はまだY町といった。そこの町で一、二を競うほどの割烹料亭「柳葉」の一人息子カズ(通称)は東京での学生時代、勉強そっちのけで趣味の写真(カメラ)と映画に夢中だった。学徒動員もされたが、結核の疑いで療養となり、前線に出されぬままに終戦を迎える。戦争も終わり、さぁ、これからは料亭を跡取り息子に譲って…などと考えていたであろう両親に、「俺はもう一度東京に行きたい。しばらくの間、好きなことをやらせてくれ」今も昔も甘い親はいるもので、「じゃぁ、もう少しな」。
しかし、順風かに見えたこの料亭商売も、戦後の激変する社会に機敏に対応できなかったのか、急速に経営が悪化していく。「倅よ、戻ってきておくれ」「まだ出て来たばっかりじゃないか」「お前の助けが必要なんだよ」「だったら、もう料亭なんかたたんで東京へ来ちゃいなよ」「そんな、おまえ〜」なんという親子でありましょう。いや、親の甘さは尋常ではない! だって、この跡取り息子は戦後すぐに、親が段取りした縁組にのって結婚し、男の子が生まれたばかりだったのですぞ。「なにを夢みてるんだ! 父親にもなったというに。このバカモンが!」と一喝できなかったのですかねぇ?「俺は東京に行く。子供の面倒は頼む」ですぞ。いまだに許した理由が理解できん。そう、残された男の子というのが、今これを書いている萬雅堂であります(笑)。
さて、東京に出たカズはいったい何をしていたのか? ずっと後年の息子(私)の詰問にも、のらりくらりとするばかり。ただ、映画関係の仕事に就きたいという希望は叶った。そのきっかけが豊島園で催された或る夜の野外映画会(そう、立てた柱の間に幕を張って…という懐かしの例のやつです)。上映中に映写機の故障。騒ぎ出す観客。さぁ、困った。その場に技術屋さんが居なかったのか、これでは再開は不可能…というときにたまたま居合わせたカズが登場!「私が直しましょう」「おお、助かった!」映写機は見事に復活して、映画会は無事終了。「あんたはいったい?」「なぁに、名乗るほどの者じゃござんせん。じゃ、あっしはこれで」…とはならず(笑)、その場でその野外映画会の関係者にスカウトされ、池袋の映画館の映写技師の職を得た。…というのだそうです。どこまでがホントの話やら。まぁ、映写技師になったのは事実だから、一応そんなこともあったのだと信じておこうか。
たしかに機械の扱いには長けていたのでありましょうか、優秀な映写技師としてひっぱりだこだったんだぞと常々申しておりましたから。きっとカズは自信満々「これで大丈夫。料亭の立て直しなんてヤメヤメ! 一家揃って東京で再出発だ! 財産処分して出て来いやぁ〜」と、Y町で待つ両親を説き伏せたのでありましょう。こうして、私の就学にタイミングを合わせる形で、一家は料亭をたたんで上京してしまうのです。昭和二十七年晩秋のことでありました。……ナンジャラホイな出だしでありますなぁ〜。
で、その約一年後の昭和二十八年秋、銀座の並木通りに邦画専門の映画館「並木座」が開館の運びとなります。この映画館がどんな経緯で作られたのかは、先般刊行された「銀座並木座」(嵩元友子著・鳥影社)に詳しく載っているので省略。まぁ、当時の日本映画関係者のクロスオーバー的な協力と尽力によって実現したとだけ書いておきます。その「並木座」の初代支配人Sさんが、映写技師長にと白羽の矢を立てたのが、私の父のカズだったのですね。前述の本に、オープンの日に劇場玄関前で撮られた記念写真が載っていますが、藤本真澄プロデューサーやS支配人と共に若きカズの姿を見ることができます。
<第11回>
連載も第十一回となりました。並木座の映写技師だった父、カズの思い出を書いているつもりが、いつの間にか自伝のようになってきましたねぇ(笑)。
で、今回分の第44号〈映画ファン教育〉の欄に思いがけない記事を発見したので、それを先ずは紹介しましょう。私が以前(第四回)に書いたことを訂正しなければいけないのです。それは「二十四の瞳」のこと。
〈映画ファン教育〉
★秋のおとずれと共にシーズンのヘキ頭を飾って、いま話題を呼んでいるのは木下恵介監督の「二十四の瞳」でしょう。
物語は瀬戸内海に浮ぶ小豆島で、時代は昭和の初めから終戦まで、高峰秀子のふんする大石先生をめぐって小学一年生から大人になるまでの十二人の──二十四の瞳がえがかれてあります。
映画は一年生時代から六年生時代へと飛ぶが、ここで出演している子役も変るのですが、一年生の子が皆んな大きくなって出てくるので観客はほほえましく驚くのです。
それもその筈です。これは皆兄弟、姉妹なのです。昨年の七月この作品をやるべく全国から兄弟五組、姉妹七組を一般募集したのです。応募は約千八百組あり、これを写真選考で約九十組に減らし、さらに、木下監督と、楠田浩之カメラマンが面接して決定したものなのです。
これで子供が似ているのはおわかりでしょうが、この子供たちが成長してからの大人の役をやる俳優も、なるべく各組の子供に似ている人を選ばねばならないのです。で松竹じゅうを探しまわったが、月丘夢路、小林トシ子、井川邦子、田村高広のほかには、既成スターの中には見当ず、文学座や俳優座の研究生を動員したり、松竹の事務員をかり出したりして配役したとの事。
※以上、原文ママ
これを読むと、「へえ〜ッ、そうだったんだ。いやぁビックリ! なるほどねぇ、そりゃそうだよなぁ…」です。
私は、「二十四の瞳」に出演の子供たちは、小豆島での現地調達だったと聞いている。と書きました。どこから出た話なの?「並木座ウィークリー」にこう書いてあるってことは、カズから聞いた話じゃない筈。結局は私のいい加減な記憶、思い込みだったんでしょうね。ここに、訂正してお詫びいたします。
今回は、もう一つ42号の〈映画ファン教育〉の記事も紹介させてもらいます。
〈映画ファン教育〉
☆真夏の太陽がじりじりと照りつける酷暑の時でもし冷房のしてある映画館に入るとひんやり感じて、しばらくは暑さを忘れて映画を見てしまう。
この映画館にも潜水艦の乗組員みたいに狭くて、熱い場所で、蔭になって働く映写技師がいるのである。客席は冷房してあるが、映写室まで冷房してある映画館はほとんどないであろう。なにしろ映写機の放出する熱量は、正にボイラーを抱えているのと同様なのであるから、ここはそれであるから冬でも扇風機をかけている職場である。
このような環境で働く映写技師は常にその映画本来の姿をスクリーンに映写して、それを画面の上に最高の効果をあらわすという苦心がある。スクリーン面の平均した照度映写レンズの焦点調節、上映フィルムの質の良否、使用カーボンの良否等…。
雨が降ったように画面にキズがあるのは一巻の映写が終るとそのフィルムを巻き直すときに傷がつくのであって、全国各地を転々と廻ったフィルムで、このようなフィルムは一年が寿命であろう。 四十度を越す映写室で上映中の映画が急に切れたりすると汗を通りこして冷汗が流れますが、又映写室は客席の上ですから観客の感動、笑い声、共感等が手にとる様に判り、こうした感激を身近に感じると張合いが出ます。 ※原文ママ
う〜ん、これを読むと、カズの働いてる様子が目に浮かぶ。私も、子供のころには何度か映写室に入り込んだ覚えがあるけど、そりゃぁ狭いものでしたね。でも、そんなに熱かったという記憶までは…無い。もしかして、この原稿はカズ自身が書いたのかしらね(笑)。
ということで、今月は「並木座ウィークリー」の記事中心でお送りしました。さて、次号は何を書きましょう…
ところがここで、「映画三昧」の楽しい〈自由が丘の誘惑〉が私を惑わせます。
幼いころからずっと、祖父母との三人暮らしが日常だった私です。けれど妹たちは両親と共にごく普通に暮らしている。なんで自分だけが父母といつも別居なんだ?と、ここらで私も「親と一緒の生活がしたいぞ!」と、思ってしまったのですねぇ。それこそ「自由が丘」には自由な生活が待っているんだと。そして、何やかんやと理屈を付けて双方を説得、高校からは両親と暮らすという決断をしたのです。カズも負い目?があるのか反対はしなかったし、私のワガママもカズ譲り。今思えば、溺愛していた孫に去られる祖父母の寂しさや、一家団欒の場に難しい年頃の男の子が突然割り込んでくることの面倒・迷惑などが分かるのですが、このときの私には到底無理なことでした。
「高校は別の学区を受けます」先生に事情を話しました。カズ一家の住いは
そして中学を卒業、ついに祖父母との暮らしからの決別です。
「ちょくちょく遊びに来るからね」と、私は気楽に椎名町の家を出て行ったのでした。
待望・念願の両親と一緒の暮らしが始まり、私がルンルン気分で高校に通い始めてすぐのこと、祖母から「おじいちゃんが入院した」との連絡が。祖父が突然、病に倒れたのです。すでに末期のガンでした。そして、祖父は七月には帰らぬ人に(まだ66歳だった)。
「ボクがこの家を出て行ったから?」「そんなことはないよ」
こうして、祖母はたちまち一人暮らしとなってしまったのです。それまでの私は、身近な人の死なんて考えたことも無い。祖父母にしてもいつまでも元気でいてくれると思っていたし、大人になったら孝行するんだ!と。この現実はショックでした。
残された祖母のことを思うとなんとか一緒に暮らしたい。目黒の家での全員同居は住宅事情からも難しいし、祖母自身が今の家に居たいと言う。私は戻りたい…戻れない…こんなことなら椎名町を出なければよかった…。つまり、取り返しがつかない決断…なんて大袈裟に書いたけれど、自分のことしか考えずに「祖父母離れ」を図ってしまったことが、今も残る私の「悔い」なのです。自分を責める日々が続きます。
そして、その高校一年の秋、初の国産TVアニメ「鉄腕アトム」の試写会に(そして手塚治虫本人に)出会った。
「コレだ!アニメーターになるっていう道があるぞ!」虫プロダクションは椎名町と同じ西武池袋線の富士見台。祖母の許に戻って二人で暮らせる。進路から大学受験はスパッと消えました(このころは「大学は美術系かなぁ」なんて思い始めてもいたけれど)。「あと二年だけ待っててね、おばあちゃん」。
迷いが消えた私は、そこからはさらに映画三昧、アニメ三昧、マンガ(劇画)三昧となります。カズが支配人をする「自由が丘松竹」はかつての「並木座」同様に、ディズニーの短編アニメ(「チップとディール」とか)を本編の合間にしばしば上映していました。私にとっては映像をたくさん観ることが、即お勉強となったのですから、カズにはまさに感謝、感謝です。
こんなお気楽な私、大学受験を控えて学業に励む級友には、ずいぶんと邪魔者だったことでしょう。とうとう三年の時の授業では、一編成だけあった女子の就職コースに混じってしまいましたとさ(笑)。
<第3回>
この夏(’07)、叔父の一周忌があり、親戚の人間が集まった。そこで再確認したことでもあるのだが、この私の、小学校入学当時の私と父の同居はごくごく短期間であったらしい。というのも上京直後に妹が生まれ、父は別所帯を構えたのだ。そう、カズは東京で再婚していたのです。おいおい、なんてこったい!
話は前後しますが、亭主が「東京に行きたい」ということで、私を生んだお嫁さんは愛想を尽かしたのですね「待っていられるものですか」(そりゃそうだって! 元々、親同士が決めた縁組で一面識もなかった。昔はそんなのが当たり前)。私が一歳ちょっとの時、実家に戻ってしまいました。当然、母親としては我が子を連れて家を出ようとしたのだが、この赤ん坊もいずれは料亭「柳葉」の跡取りになる人間とばかりにそれは許されません。泣く泣く、乳飲み子を置いての離縁です。なんと不憫なこの私…あっという間に両親が不在となりました。つまり、徐々に傾いていく料亭で「祖父母と孫」の三人暮らしとなったのですね。そんな家庭内の事情は知る由もなく、萬雅堂は無邪気に田舎で幼年期を過ごしていたのです。
さて、父と再婚した人も、新婚の所帯にいきなり田舎から亭主の両親と先妻の子供が押しかけて来たんじゃたまらない。そりゃ、別に暮らしましょうよとなりますわな。まして、二人の間に赤ん坊が生まれるのですから。なんとまぁ、自由人でありますよ。カズさんは!
勤務先の「並木座」に近い場所ということだったのでありましょう、父たちは麻布の借家で暮らすことになり、またしても私たちは三人暮らしです。倅のためにと料亭をたたんで上京した両親は、いきなりハシゴを外されたようなものですな。ヤレヤレ、どこまでお人よし。こうなれば心の支えはただ一人。溺愛の対象は「倅から孫へ」と変わっていくのは必然です。こうして、私は究極のおじいちゃん子&おばあちゃん子になっていくのでありますよ。やだねぇ、カズと同じようなわがままな甘えん坊が又一人出来上がるぜ。チャンチャン!
で、余談でもありますが、この東京の家というのが、な、なんと!のちに漫画界で伝説となるアパート「トキワ荘」の至近、椎名町5丁目(2164番地)なのであります。狭い街並みの路地数本を隔てただけの、子供の足でも歩いてすぐのその場所に「トキワ荘」は在りました(同2253番地)。そう、手塚治虫が「漫画少年」の紹介でこのアパートに入居したのが正に同時期であります(昭和28年と書き残している。おそらく年初ですね)。寺田ヒロオの入居が手塚から一年後で、その寺田を訪ねて昭和29年に高岡から安孫子素雄がやって来ます。で、その年の暮れに手塚が出て行くと、その部屋に藤子不二雄(安孫子&藤本弘)の二人が入る。翌、昭和30年、石森章太郎の入居、さらに赤塚不二夫…となるわけだ。彼ら新人漫画家たちが毎日必死で作品と格闘している最中に、その「トキワ荘」の周りで何も知らずにワイワイ遊びまわっていたのが小学校低学年当時の私たち、彼らに言わせれば「近所の悪ガキ、いたずら坊主ども」ですね(笑)。
<第5回>
ドスッ!…ギラリ… 顔前に鋭い刃が光る。カズの座る机に男がいきなり、ドスを突き刺したのだ。
「さぁ、ショバ代を貰おうじゃないか。とっとと出しな!」
オープンしたばかりの銀座並木座の事務所に、或る日、とある組織の人間が現われた。(はて、どこの組? 詳しい人なら○吉会や○葉会、○粋会や○東組とかの、当時のそっち方面の名前がいくつか浮かぶでしょうが、私はそこまでは聞いてない。)しかしそのとき、カズは少しも騒がず、
「せっかくだけど、うちはそんなものはビタ一文出せないね。さぁ、お引取り願おうか。」
「なんだとぉ? てめぇ、でけぇ口叩きやがって!」
「実は私は○○さんのところでかつてお世話になった者でね。なんなら○○さんにこのことを伝えようか」
「な、なにぃ?…チッ、ならば、仕方がねぇ。ま、今日のところは見逃してやるぜ」
机のドスを引き抜くと、男は立ち去り、以後二度と現れることは無かった。なんだか、下手なドラマや古臭い劇画によく見るパターンですねぇ。コント的展開になりそうだ(笑)。
興行の世界と、あちらの世界とは、昔からさまざまな形での、腐れ縁的な関係が語られています。銀座にもヤクザさんは当然いたでしょうし、このカズから聞いたエピソードも、あながち嘘ではないのでしょう。
映画人たち有志の共同出費で作られたような、大資本が後ろに控えていない、独立した小さな一映画館では、こういった方々の要求から身を守ることはなかなか難しい。毅然とした態度で拒否するのが一番効果的と分っていても、目の前にドスを突きつけられて迫られてはねぇ…。度胸あるよなぁ、カズは。
「○○さんの…」というのは、カズのとっさの出まかせではなく、実は学生時代に本当に或るヤクザの親分さんのところに下宿?というか、一時期、寝泊りさせてもらっていたのだそうです。学生の身ですから、あくまで「お客人」で「組員予備軍」などではありません。とても丁寧な扱いを受けていたけど、卒業したら入社します(内定!)、ってことでも無かったそうだ(笑)。割烹料亭の一人息子だったから、客商売でつねにいろんな人と交流があり、たとえ組織の親分さんであろうと、人の懐にすっと入り込むのなんか、いとも簡単だったんでしょうね。カズにとっては。(いやぁ「学生ヤクザ」になってなくて良かったなぁ…)
他の映画館に移ったり、のちにパチンコ屋、ボウリング場、ゴルフ場の支配人なんかもやってたときも、この世渡り上手ぶり?を存分に発揮してたのでありましょう。
<第6回>
うーん…正直、並木座の記憶はもう無いなぁ(笑)。この並木座のプログラムは同じ版型で157号までを、以後三分の二サイズにして昭和32年暮れの190号で休刊、半年後に復刊して191号、以降は平成10年の閉館までいろいろと形(と名前も)を変えながら発行し続けたとのことです。カズが遺してくれたのは100号(昭和31年2月)まで。それ以降が無いのは、カズが並木座を辞めてしまったからなのですね。なぜ辞めたのか? ハイ、それは「生活のため」なのです。昭和29年に次女が生まれ、カズには一家七人の暮らしを背負う重責が…嫁さんと娘二人のほかに、祖父母と私の生活費もありますから大変です。並木座(株式会社だ!)は、支配人、経理担当の他、営業一人、出札(テケツ)・もぎり・案内係の女性従業員六人、映写技師二人、同見習い一人の計十二人の社員で切り回すという小さな小さな映画館ですから、昇給もままならなかったのでありましょう(映写技師長といっても名ばかりですしね)。
少しでもお給料の高い職場を求めて彼は放浪し始めます。先ずは、私たちが暮らす椎名町の家から歩いて通える映画館「目白映画」に移った。私はうろ覚えだが、少しの間はふたたびの同居生活だった筈。この「目白映画」は私の家からトキワ荘の脇を通って徒歩数分のところに在った映画館で、松竹系の封切館ではなかったかな。東宝映画も上映していた気もするが…私が覚えているのが久我美子主演の「挽歌」だ。扉が閉まらないほどの満員だった。小学生が観たって分かるわけは無いのだが、きれいな人だなぁ、と思ったことだけは(ませたガキだぜ!)。調べてみたら、昭和32年の8月の封切り。ということは私は小学4年生か。
で、この頃から私は映画を盛んに観始めます。家の近くには他にも東映(そういや、第二東映なんてのもあったな)や、たまに新東宝の映画を上映する「長崎東映」と、洋画の二本立て上映の「平和シネマ」という映画館が在り、どちらもカズの段取り(口利き)で、タダで入場していた。顔パスというほどでもないのだろうが、いつだって好きに観ることが出来たのだった。小遣いをあげられない代わりに、せめて映画くらい、ということだったのかもね。
ちょうどこの頃には「東映スコープ」っていうワイド画面の登場だ!東映オールスターの「忠臣蔵」、「大菩薩峠」の片岡千恵蔵、「水戸黄門」の月形竜之介をはじめ、中村錦之助、東千代之介、大川橋蔵のチャンバラ映画に夢中になり、「白蛇伝」(昭和33年)「少年猿飛佐助」(同34年)「西遊記」(同35年)「安寿と厨子王丸」(同36年)の東映動画作品に触れたのがこの「長崎東映」だったなぁ。
新東宝映画では嵐寛寿郎の「明治天皇と日露大戦争」と宇津井健の「スーパージャイアンツ」を覚えてる(吊ってるロープが見えた!)。
「平和シネマ」で観たのは…「砂漠は生きている」(ディズニーの記録映画)くらいか。
松竹系映画では仲代達矢・新珠三千代の「人間の条件」(昭和34年)だが、暗いモノクロの画面しか印象に無い…あ、それでも仲代が「覚えておきたい」って新珠の裸を所望するのは子供には強烈だったなぁ! 同じ戦争モノでも、伴淳三郎・アチャコの「二等兵物語」には笑いこけてたけどね。
東宝では「ゴジラの逆襲」(昭和30年)がかすかな記憶、「ラドン」(同31年)から胸躍り、「地球防衛軍」(同32年)「宇宙大戦争」(同34年)が最高潮!これ、確か毎年のお正月興行だった。大映・日活は、小学生時代はとんとご縁がありませんでした。ハイ。もちろん洋画もですね(笑)。
さて、カズですが、「目白映画」も長くはおらず、彼は次に西武池袋線の清瀬に在る「清瀬映画」に移ります。私は(おそらく6年生)一度だけお弁当を届けに行ったことがあるのだが、なんとローカルな駅と映画館だったことか!駅はプラットホームが低く、スロープから遮断機を抜けて線路を渡って改札に出るという奴だし、小金井街道沿いの映画館は、映写室の脇に畳敷きの小部屋があってね、そこでカズと一緒にお弁当を食べたっけ。だんだんと都落ちしていくみたいな気もしますが(笑)この先、一家の運命や如何に…?
まぁ、このSさんとは以降数十年、亡くなるまでのお付き合いが続くんだから、もう実の兄弟みたいなものですね。私などには窺い知れない深ーい結びつきがあるのでしょう、きっと(私の「身元保証人」ということにもなっていた)。勤務地が目黒ということで、カズ一家は再び私と祖父母が暮らす椎名町から去っていきました。新しい住まいは…不明(笑)。
では、腕利きで鳴らしたカズは目黒スカラ座の映写技師になったのかというと…これが実は実はでありまして、Y手興行というのは文字通り「興行」会社でありますから、やっているのが映画館だけではないのです。カズに与えられた職責は、な、なんと、「パチンコ屋の支配人」だったぁ〜〜〜ッ!!!
このパチンコ屋さん、目黒スカラ座の手前隣に在りました。当時のパチ屋(こう呼んでいた)は、台の裏側に狭い通路があって、「オーイ、出ないよ」台の上からおねぇさんが顔覗かせて「どうしました?」なんてね(笑)。カズ一家の住まいは、不明の筈だよ、そこの住み込みだったのだ!小学校の6年生だったかの私は何度か遊びに(?)行ったことがあるけど、カズはパチンコ台の扉を開けて、短い金属棒の先にパチンコ玉が溶接されてる奴で釘の撥ね具合を確かめたりの、いわゆる「釘師」って奴をやってましたよ。曲げた人差し指の上でその金属棒を微妙に上下させて玉を釘に当てる。これが、けっこう面白い(笑)。だから、私も台の裏側のメカニズムなんかを感心して見ていた「へぇ、こうやって玉が流れていくのかぁ…上皿と下皿の玉の重さで台の傾きが変わるとはねぇ」。従業員の部屋に置いてある研修用の台で打たせてももらった。「天のこの位置を狙って打つんだ。ここの釘の開き具合が決め手だぞ」なんて十二歳の息子に教えるバカ親の指導の下で。しかし後年、私にはこれがとっても役に立ったのですな(余談・笑)。
妹たちはそろそろ学齢だし、さすがにこれは良くないと思ったのでしょうか、ほどなくカズはY手興行が新たに自由が丘にオープンした映画館「自由が丘松竹」の支配人となりました。今にして思えば、おそらくその約束での清瀬映画からの引き抜きだったのでしょうね。劇場が出来上がるまでの間、ちょっとだけ頼むよという「釘師」役。なんたって腕の立つ技術屋さんだからね、カズは(ヤーさんにも顔が利くし・笑)。
なかなか映画の中身の話が出てこないね、今回は。まぁいいか。「自由が丘松竹」は文字通り、松竹映画の封切館です。そこの話は次回にでも。
<第8回>
開館となった「自由が丘松竹」。これは当時、邦画の名画座として在った映画館「自由が丘名画座」が、松竹系の封切館として生まれ変わったものと記憶している。オーナーが同じだったのかどうかまでは私は知らない。もう半世紀近くも前のことだし、当事者ではないので(笑)。カズはこの劇場の支配人となったのです。この時のカズは三十代半ば、豊島園での野外映画会の場で映写技師としてスカウトされて以来約十年。まぁまぁのキャリアアップだったといえましょう、でも、一家七人の暮らしを支える現実に変わりはありません。厳しい生活はまだまだ続きます。
さて、この自由が丘松竹、さほどの客席数ではない(せいぜい二○○?)。二階席は無く、二階の位置には映写室と、住み込み従業員の部屋が長い廊下沿いにいくつか有るだけという小さな劇場だった。もっとも、この自由が丘は他にこういった映画館がいくつも在るという土地柄。すぐ隣には東宝映画の封切館「南風座」。道を挟んだ向かいには大映映画の「ロマンス座」(この劇場でフィルム運びのアルバイトをしていたのがボクサー当時の「カッパの清作」こと斉藤清作、後の「たこ八郎」。自転車の荷台にフィルム缶を積んで走っているのを私も見かけた。当時からユニークなボクサーとして話題だった・余談)。ちょっと離れて東映系の「武蔵野館」。駅から続く東横線の線路沿いの商店街ビル二階には日活映画の「ヒカリ座」。ガードをくぐっての場所には洋画三本立て上映の「自由が丘劇場」と、なんと!この狭い街に六館も。つまりは、それだけ映画全盛の時代だったということ。昭和三十年代前半です。
カズ一家は当初は他の従業員同様に住み込みだったが、小学生となる娘の住所が「映画館内」では可哀相と、すぐ隣の緑が丘に家を借りることに(といっても戸建て二世帯住宅の二階部分)。こうして職住一緒という生活は短期間で終わりを告げたのです。ヤレヤレ。
私といえば、当時すでにすっかり映画にはまっていましたから、この自由が丘は羨望の地と化します。中学生になったし、一人で出歩けるからと、休日は「映画の日」とばかりに、椎名町から電車を乗り継いで自由が丘へと通うのです。時には前日から泊りがけで(といっても毎週じゃないよ)。カズの手元には常に前記の全劇場の招待券があるから、私はいつだって観放題!まさにこの世はバラ色です(笑)。こうして、小学校の頃には馴染みの無かった大映、日活の映画や、洋画も観るようになったのでした。さらには、「渋谷パンテオン」といった洋画ロードショー劇場や、その東急文化会館地下のニュース映画専門館にまでも鑑賞範囲は広がっていくのです。
だいたいがその場限りのお楽しみっていう観方だし、中身なんて殆んど覚えていない。このころどんな映画を観ていたのか、とりあえずタイトルだけの列挙をしてみましょうか…
☆「自由が丘松竹」ではトニー・ザイラー主演の「銀嶺の王者」。なんでこんなの覚えているかというと、共演の鰐淵晴子が母親と共に観に来たところに遭遇したのだ(凄いオーラが!)。松竹ヌーベル・バーグの「青春残酷物語」「太陽の墓場」「乾いた湖」と、小津の「秋日和」。岩下志麻の「あの波の果てまで」。独立プロ作品の「キクとイサム」。
☆「南風座」では森繁の「社長」シリーズと「駅前」シリーズを。岡本喜八の「独立愚連隊」。オールスターものの「日本誕生」「太平洋の嵐」や「娘・妻・母」「がめつい奴」「用心棒」。黒澤プロ作品として「悪い奴ほどよく眠る」。
☆「ロマンス座」では…うーん、勝新の「悪名」くらいしか思い出せない。「座頭市」「兵隊やくざ」はもう少し先となる。
☆「ヒカリ座」はもちろん旭の「渡り鳥」シリーズですね。なぜだか裕次郎は敬遠?していた。
☆「武蔵野館」は錦之助の「宮本武蔵」かな。
☆「自由が丘劇場」はろくなもの観ていない(失礼)。オーディー・マーフィーの西部劇とか、ボップ・ホープの喜劇とかばっかりね。
まぁ、こんな映画三昧の生活を送るお気楽な中学生は、私くらいのもの。この後、高校進学の転機に、私は人生において取り返しのつかない(今となっては悔やまれる?)決断をしてしまうのであります。それは…次号だ。
小学校の低学年のころからの愛読書は雑誌「少年」(光文社)でした。連載マンガ「鉄腕アトム」に夢中の、ごく当たり前の男の子。祖父母と私の三人暮らしだからといって、毎日を茶飲み話で過ごすはずもなく、近所の子供と外で遊んだあとは、家で一人、マンガの世界に入り込むのは必然だったのでしょう。
高学年ともなると、自分でもマンガらしきものを描くようになるし、日々、人気マンガの主人公を模写してばかり。で、上手く描けたりすると読者ページ宛に投稿を始める。「少年」だけでなく、他の雑誌を友達から借りたりして、(当時の雑誌は「少年クラブ」「少年ブック」「少年画報」「漫画王」「冒険王」あたりかな)小学六年生から中学一年生の頃は各雑誌の読者ページに手当たり次第に投稿していた(ハガキに黒インクで描くんですよね)。それが高確率で採用され、バッジやら鉛筆の賞品ゲットに鼻高々でした。最優秀でグローブを貰ったりもして。正規読者でもないのにひどいものです(笑)。
ですが、折からの劇画の登場、すぐに興味は移ります。もう中学生。子供相手の月刊マンガ雑誌なんか卒業だ!ってなもんです。背伸びしたい年頃なんでしょうね。近所には貸し本屋さんが何軒かあり、ちょっと大人びた「影」とか「街」の単行本シリーズに夢中となります。貸し本屋通いがまるで日課のようになりました。辰巳ヨシヒロ、さいとうたかを、佐藤まさあきあたりが代表格ですかね。ちょっと個性が強い山森ススム、松本正彦とか、桜井昌一、石川フミヤス、K・元美津なんて名前を思い出す。「劇画工房」ってやつですか。
「影」「街」の他にも「摩天楼」「顔」「刑事」なんていうのや、作家個人の「台風五郎」シリーズ(さいとうたかを)、「影男」シリーズ(佐藤まさあき)みたいなのもあった。どれにも読者ページがあり、私は当然の如く、劇画の主人公を模写して投稿に熱中(「台風五郎」には「五郎やん似顔絵コンクール」なんてのまで)。劇画誌の場合は、掲載されると、なんと、作家の切り落とした生原稿数コマがご褒美でした!(凄い時代だ・笑)
さらには、読者同志の交流を目的とする「同人」サークルの会員募集が毎号のように載っていた。それこそ日本中のあちこちで、劇画少年たちが競って同人誌を発行、同好の仲間を募っていたのです。私が迷わず参加したのは言うまでもありません。みんないくつも掛け持ちで参加しています。私も複数のグループの会員になりました。会誌名で列記すると「若鮎」「ふぁいと」「アンパン」「Gメン」「ナイト」「ジャンプ」「アトリエ」「Z」なんていうのが、何冊か今でも私の手元に残っています。もう半世紀近くも前の、どれもが、わら半紙に謄写版インク(ガリ版ですね)が染み込んだ、茶色く、ボロボロになった代物ですが、その手書き文字の幼さが懐かしくもまた泣かせます。それぞれ会員のカットを載せては採点ごっこをしたり、いっぱしの劇画論を戦わせていたりね。
二年生も終わろうかという頃、私は近所の古道具屋さんの店頭に謄写版セットを見付けてしまったのです。これはきっと「お前も会を作りなさい」との天の思し召しに違いないと、迷わず購入、サークル作りを決断しました。そして会員募集をかけます。それは「顔」28号でした。※どの本に告知したかなんて、とうの昔に忘れていたら、数年前に「広場」会員でもある
全国から十数名の会員が集まり、クラスのマンガ好きも誘い込んで、二十名ほどで会は発足しました。その会の名はなんと「文無し劇画クラブ」(別称が「ノーマネー・クラブ」)(笑)。そして三年生の五月に会誌「おぜぜ」第一号が発行されました。
で、六月に会誌の第二号を発行したあと、丹精込めて編集・製本した分厚い肉筆回覧誌「おあし」第一号をも発行したのですが、発送、即、行方不明となり大ショック! 茫然自失の夏休みを過ごした私は、休会を宣言してしまうのです。意気込んで始めた活動は、こうしてあっけなく終わりを告げ、手元には編集途中の「おあし」第二号だけが残されたのでした。
あらあら、紙数が尽きた。「決断ばなし」は結局順延ですね。
……ということで、第25回(最終回)
カズが田舎で暮らし始めて最初のお正月、カズの新居には、子供たち三家族の全員が大晦日から集合していた。孫も数人が賑やかに走り回っています(毎年一人ずつ生まれていた)。
カズの年頭挨拶、「おめでとう! みんな今年も良い一年であるように」そして年長の孫から順番にお年玉を手渡す。一族の長としてのセレモニーだ。その後、初の8ミリ映写会が開かれたのであったが…妹の家族の映像が数分映っておしまい。
「これだけ?」
「ああ、付いてたフィルムの分だ」
「他にないの?」
「フィルム代がなぁ、けっこう高いんだよ。今後を考えると、現像のこともあるし、やはりビデオだな。なぁおまえビデオを」
「……(呆)……」
還暦祝いに8ミリをねだられた顛末がこれ(なんだよ〜ッ!)。我が家族の映像はついに未撮のままでありました。ヤレヤレ。
カズは悠々自適を気取るのか、「所詮は年金暮らしよ」と言いながら働くこと(いわゆる再就職)はせず、幼なじみを家に集めては楽しい日々を送っていたようです(中央競馬の電話投票権をフル活用)。集落ではたちまちに「顔」となり、自治会長を引き受けたりして偉そうにも。自ら立候補はしないものの、もっぱら「頭」と「口」で地方政治にも首を突っ込む。まぁ、私の予想通りですかね(笑)。それでも敷地の半分を畑にして、自家用の野菜づくりには熱心でしたっけ(私の許にも、ときどき段ボールいっぱいのジャガイモなどが届く)。
そして幸せな十数年は、あっという間に過ぎていく。
「ねぇ、田舎でのんびりもいいけどさ、ひとつ自伝でも書いてみない?」「自伝?」「そうだよ、波乱万丈の人生を送ったんでしょ? 子供や孫たちにそのあたりのこと書き残しといてくれなくちゃ! 勿体ないじゃないさ」「それもそうだな」
私のくすぐりに、カズはその気になった。実はこれ、カズの〈喜寿の祝い〉の席でのことである。
カズは、さっそくコクヨの原稿用紙の束を買ってきて執筆を開始したのだが…その数ヵ月後、突然の病魔が襲う。いや、病は「潜伏」していたに過ぎず、発覚しなかっただけ。体調不良は自覚していたのかもしれないが、頑迷な性格(周りの忠告、進言は聞かない)が邪魔をしていたのだろう、町医者の「単なる○○ですよ」の言葉を信じ、更なる検査を怠ったのだ。「病巣さえ取り除けば、あと数年は平穏に…」という大学病院での診断に、カズはようやく入院を決めたのだが、その手術後に、自身が思うほどに体力は回復せず、帰宅はついにかなわなかった。…最後まで、自分の思いのままに生きたのだから、この結果もきっと「納得」なのでしょう。
カズの書きかけの「自伝」が私の手許にある。それは400字詰めで4枚半、「さぁ、これから書くぞ!」というマンマンの意気込みで終っている(笑)。出だしだけでも紹介してやろう。
「大正十一年七月十六日、一人の男子が此の世に誕生した。女性だらけの家庭に初めてチンボコのついた赤子が生まれたので、両親の喜びはいかばかりであったろうか。物心のついた時、蝶よ花よと育てられた所を考えると、大吉をひいたと感じたのであろう。朝から晩まで女に抱かれて育ったことが私の宿命だったかもしれない。幼稚園に通っていた時、今も忘れられない○○子先生が私のスタートだったから…」
おいおい、まさかの女性遍歴かよ! 最初から笑わせてくれます。小中学校時代、いかに文武両道に秀でていたか…とか、優等生として同級生から絶大の信頼を集めていたとか、自慢・傲慢のオンパレードです。いやぁ、残念だ。こんなことならせめて数年前にけしかけるべきだったなぁ、きっと「大傑作」が遺されたであろうに… そして、「これから大学時代の話にうつる」で原稿は終っています。
私はカズの大学卒業後から約半世紀ほどのお付き合い(?)。それも付かず離れずの奇妙な関係です。この二年間、この連載を書くことで、父親カズを心の中に再生してきました。カズの未完に終った「自伝」を、私が成り代わって書いたということなのかもしれません。ただ、大学時代が空白のまま…これは永遠の謎であります。きっと、ここにカズと「映画」との関わりの何かが隠れている…と私は睨んでいるのですがね。
<完>
<第22回>
私が念願かなって虫プロのアニメーターとなって二年、私と祖母との二人暮らしに異変が…祖母がある日を境に「別の人」となってしまったのだ。話すことの端々がどこかつじつまが合わない。亡くなった祖父がこの場に居るような、昔に暮らしているようなことをしゃべるのだ。医者の診断は「軽度の脳軟化症」(脳梗塞)だった。話はかみ合わないものの身体の方は元気、外見からはとても病人には見えない。家の中での日常生活に支障はなく、投薬での治療となった。私は心配ではあったが自宅で一日付き添っているわけにはいかない。現場は忙しく、だましだましの数ヶ月…いつものように虫プロで泊りがけの仕事となったある朝のこと、隣のおばさんから虫プロに電話が入った。
「あ、雅一ちゃん、おばあちゃんの様子がおかしいの」
私が家を出るときは何の予兆も無かったのに…その日、祖父と同じ六十六歳という若さで祖母は逝った。こうして、私は二十一歳で椎名町の家に一人暮らしとなってしまったのだ。
茫然自失、こうなると私はもう糸の切れた凧であります。誰もいない家に帰るわけがない(笑)。深夜残業は大歓迎、たまの定時退社も友人との夜遊び、徹夜マージャン…外泊の連続。ムチャクチャ仕事もしたけれど、めちゃめちゃ遊び呆ける毎日。そしてお決まり、「神田川」の生活に突入。♪小さな石鹸カタカタ鳴った〜♪ 何も怖く〜なかったわけですねぇ。
すると、私が暮らさないのならと、椎名町の家にカズ一家が戻った。何たるこっちゃ!(呆)いや、これには理由があって、カズがまたしても異動となったのだ。映画、パチンコ、ボウリングときて、さて今度は…そう、ゴルフ。このころ、日本の高度成長は、ついにゴルフまでをも庶民の手に届くレジャー産業にしてしまった。世は空前のゴルフブームに。数百万、数千万の会員権が飛ぶように売れて、開発業者はウハウハ! 日本中の山や畑が競うようにゴルフ場へと変貌を遂げていきます。カズの会社も当然の如くにブームに便乗、ゴルフ場開発競争に参入する。もう、私も少々のことでは驚かない。土地の買い付けからのもろもろを任されたカズは単身、福島県への長期出張となったのだ。東京近郊ではないところが小企業の悲しさかな、資金力が無いから、どうしたって遠方となったのだろう。カズは現地に居を構え、毎日が土地の買収話。人の懐に飛び込むことに長けたカズの本領発揮です。地方の純朴な人々はおそらくひとたまりもなかったことでしょう。彼、四十代後半から五十歳の頃でありました。つまりは女房と娘たちは椎名町の家でお留守番ということ。ようやるよなぁ…しかし。
かくして数年、郡山近郊にそのゴルフ場はオープンした。そして勿論のこと、カズはそこの支配人となったのだ。この数年間、私とカズの交流は殆んど無かった。あっちは福島に行きっぱなしだし、私は既にフリーになっていて、アニメーションにどっぷりの毎日。別に連絡し合うこともないから(父親と息子なんてそんなもの・笑)。ただ唯一、私が結婚することになって、その前後にバタバタとした行き来があった。
私の場合、いわゆる職場結婚みたいなもので、相手は私が虫プロを辞めた後に創られた「虫プロ・アニメーター養成所」の一期生。だから、後輩ということになるのか、フリーになった私が机を借りる形でスタジオに戻って、そこで出会ったわけだ。ずっと以前、カズは私にしきりに見合いを勧めている。おそらく何か企んだのだろうが、もうその手には乗らない(笑)。で、この結婚話をカズに伝えると、慶事がカズの「興行師」としての血を目覚めさせたのか、「挙式はどうでもいいから、披露宴をオレに仕切らせろ」と言い出した。私は、相手が小さい頃から日曜学校で通っていたという教会で式を挙げ、引き続き友人たちとささやかなパーティーを開くことを考えていた。蓄えなど無い私には豪勢な披露宴を開くことなど思い及ばなかったのだ。金の心配は一切要らんからと言うカズに、
「…じゃ、任せるよ」「よーし!」
こんな経緯で行われた挙式当日夜の披露宴はというと…案の定、新郎側の招待客は数人の親戚・友人以外は「見知らぬ人ばかり」。つまり、大半がどこぞの会社の偉いさんたちだった。なんだ、結局はカズ自身のためなのねぇ(当然のこと実母の列席は無い)。でも、感謝はしております。名高い結婚式場「G園」での格調ある披露宴、これも親心の発露なりか。
編集のFさんをリーダーに、制作、アニメーター、美術のスタッフの計8人が集まった。名付けて「タック・マスターズ」。名前はやけに立派だけど、Fさん以外は殆ど全員が初心者という、なんとも頼りない同好会であります。それでも全員がとりあえずのゴルフセットを購入、暇を見つけてはスタジオ近くのゴルフ練習場へ通うこととなりました。これ、1977年秋のことであった。
そして早くも明けて78年1月に初コンペの決行だ! こうして、「ゴルフって、なんて面白い!」とばかりに、以降、隔月のコンペ開催が決定した。そして11月の第6回コンペに於いて、ついにカズが待ち受けるゴルフ場への遠征となったのである。
当時、東京から車で4、5時間はかかった福島県では早朝の出発というわけにはいかない。前日からの初の泊りがけゴルフとなった。数台の車に分乗してドライブがてら東北道を走る。インターを下りて一般道、山道をさらにクネクネ…ようやっと辿り着いた夕闇のゴルフ場。入口ではカズが一人出迎える(従業員は既に帰っていた・笑)。私も久々の対面だった。カズは単身、ゴルフ場に隣接の宿舎で寝泊りしていた(プレハブじゃん)。そして我々は(カズ精一杯のもてなしを受けた後)ゴルフ場内の立派な宿泊施設に泊まる
「いろいろありがと!」
「楽しんでけよ」
「たまの子供孝行もいいもんでしょ、こっちも営業に協力してるんだし」
「何を言ってる!」
…というのは二人だけの会話だ。
夜に降り出した雨も朝には上がり、そして秋晴れ。カズのサポートもあって全員が楽しい一日を満喫したのでありました(当日の記録によると、私はブービーだ)。ただ、その遠さに懲りたのか、ここでのコンペはこの回限りとなったのです(笑)。
ゴルフ目的ではなかったが、後年、私や結婚した妹の家族たちと、身内での旅行で一、二度訪ねたことはあった。
やがて…長年に亘るゴルフ場への関わりも終わりを告げ、久方ぶりに東京に戻ったカズは、いつの間にか五十代も半ばになっていた。福島での一人暮らしの間に、いろいろと考えるところがあったのだろう、カズは老後に暮らす為の家を故郷に建てるという決意を固めていた。
「おい、いくらか用意出来んか」
突然に、私の前に現れたカズが言う。要は家の建築費用の一部を援助しろということだ。
「すぐに返すから安心しろ」
既に家庭を持っていた私だから、一存で返事は出来ない。しかし妻だって義父に即「ダメです」とは言えない。子供はまだ授かっていないときだったし、なんとかかき集めて手渡した。
「お金を貸す場合は、戻ってこない覚悟(あげるつもり)で」というのは至言です。正直に「援けてくれ」とは言えないカズだ。そして「返さなくても(奴なら)分かってくれる」と考えていることも、私にはお見通しです。借用書なんて書くはずもありません。この件、そのまま…カズは口を閉じて…終ってしまったことは言うまでもありませんね(苦笑)。
この件、自由が丘に戻った私は一切黙して語らなかったが、祖母からカズに伝わった。いきなり(継)の字が付いてしまった母はうろたえ、カズは秘密?を口外した面接官に対して憤慨するという、可笑しな反応を見せた。
分かってしまった以上、今更ジタバタしたって始まらないということなのか、「(実はそういうことなんだが)もう、俺は知らんぞ」ということなのか…(開き直りかい・笑)。カズは一言もこの話題には触れないし、それならいいさと、私も聞かない。以来、実母問題は父と息子の間の暗黙の了解ごととなっていく。継母のためにもそれがベストなのだから、コレでいいのだ!
さて、倅の卒業式は迫っている。就職は決まらない。どうするカズ! そう、カズはついに本気になって私の就職のための行動を開始した。今日は印刷会社、明日はデザイン事務所と、なんだか気乗りのしない私を連れての会社めぐりが始ったのだ。といっても全てが「つて」を頼ってのこと。一応、絵に関係する業種を選ぶところは私に対する気遣いなのだろうが。どこも今ひとつ心動かされない…とうとう就職先が決まらないまま、私の高校生活は終った。春休み…じゃないなもう(笑)。
進路が決まらないまま、桜の花が咲く四月となった。そして、さらに行脚が続いた或る日のこと。小さな映画配給…だったか制作会社だったかを訪れたとき、「アニメーターになりたいんだったら、私が紹介してあげようか」と、言ってくれた人がいた。(そこのプロデューサーのような人だったが、名前は忘れた。恩知らず!)「タツノコプロダクションっていうんだけどね」「え?」聞けばマンガ家の吉田竜夫、九里一平兄弟が自分たちのアニメ作品を創るために興した、まだ新しい会社だという。この二人の名前は知っていたし、九里一平の描くマンガは、むしろファンと言っても良いくらいに読んでいた。その人たちもアニメーションを……。東映と虫プロ以外にアニメのスタジオがあることを知らなかった私は「ぜ、ぜひ、お願いします!」
数日後、その人の紹介状を手に、西武国分寺線「鷹の台」駅を降りた私は、畑の中の細い道をまっすぐ「タツノコプロダクション」のスタジオに向かった。もちろん一人で。もう、ここから先は自分で切り開いていかなくては…。
雑木林に隣接したスタジオは、なんと小さな…いや、東映動画と較べちゃいけませんね。そう、二階建ての、とても親しみのもてる建物でした(笑)。面接していただいたのは吉田三兄弟の真ん中、健二さん(当時専務)。今となれば、そのときに何を話されたかなんて、全く覚えていないが、優しい口調の、温和な印象だけは記憶に残っている。何か描いたものを見せるでもなく試験もなく、その場で即、採用が決定しました。あっけないこと、この上なし。ふぅ…今までの経緯は何だったのよ?
すぐにカズに報告(「そうか」だけ)。紹介してくれた人にはカズから連絡(御礼は…はて?)。
こうして四月の半ば、アニメーターの卵がようやっと産み落とされた。はたしてこの卵、無事に孵化するものやら… 初任給は14000円。三ヶ月の試用期間が終って1000円のアップという、かつて東映動画で聞かされていたものの半分ですけど、もう、金額なんかどうでもいいやね。
タツノコプロに通い始めて間もない頃、つまり祖母との生活に戻ってからすぐに、祖母が突然、私に問いかけます。「おまえ、ホントの母さんに会いたくないかい?」「え?」「会いたかったら連絡を取るよ」「……」とっさには返事が出来ない私。「だって、おまえも会いたいだろう?」「…(そうでもないけど)…」「親戚の娘さんだから、知らせてやればいいだけだよ」「親戚…」そうです、もともとは親同士の一存で決めてしまったカズの結婚でした。新郎新婦が一度も会ったことの無いまま式を迎えるという、当人同士にとってはムチャクチャな話の…
さらに詳細な話を聞くと、親戚というのはなんと祖父の弟だった。「え〜ッ!Sおじさんの?」「そうだよ、その娘さんだ」「じゃ、じゃ、…いとこ同士の結婚?」「まぁ、そういうことになるかね」Sおじさんには私は何度も会っています。祖父は男ばかりの四人兄弟の次男坊、Sおじさんは三男坊で、この二人はとても仲が好いのです。そして、Sおじさんは私をとても可愛がってくれていました。「(そういうわけだったのか…おじさんにとっても、ボクは孫にあたるんだ!)」父方の祖父は亡くしてしまったけど、母方の祖父が健在だ。それがあのSさんだったなんて!祖父の葬儀の時のSさんの姿が思い出されます。
私の頭の中はもうゴチャゴチャです。そんな関係ならばこの先の展開を考えると、「我関せず」と言ってばかりはいられないでしょう。この際、この事実をはっきりと受け止めなければいけません。心は決まりました。「会うよ」。
そこから先、祖母がどのようにして連絡をつけ、どう段取ったのかは分かりません。しばしの後、十七年だか十八年振りの母と子の再会が実現します。
場所は渋谷駅前。会ったのは二人だけで介添えは不在。どうやって待ち合わせ、なぜに当人同士と分かったのか…今はもう判然としない。私は母の顔を知らないし、指定された場所に待っているだけ。ひょっとしてSおじさんがどこかにいたのかもしれません。「ホラ、あの子だ」と言って母の背中を押したのかも。それからどこかの喫茶店に行き、どのくらいの時間、どんな会話をしたのだろう…おそらく殆んどが母の身の上話だったはずだ。カズとの結婚のいきさつやら、別れの決断、私への想い、その後の生活のこと…私はただ黙って母の話を聞いていた。ときどき短い返事をしながら…。
目の前の人が自分を産んだ母なのだ、という実感をすぐに抱けるはずもなく、どこか客観視している自分が分かるのです。
きっと、我が子との突然の再会に、母もどう対応してよいのか分からなかったのでしょうね。沈黙が怖くて話し続ける。別れ際、分厚い封書を渡されました。「あなたに会って、何もしゃべれないかもしれないと、昨夜この手紙を書いたの。あとで読んで」「はい(しゃべり通しでしたけど…)」それが可笑しい。
今も残るその手紙、ところどころに涙の滲みが分かる、私の宝物デス。
「週刊漫画サンデー」(実業之日本社、1959年創刊)と「週刊漫画TIMES」(芳文社、1956年創刊)がそれだ。これらの雑誌、カズは創刊時から読んでいたんじゃないのかな、私が中学生になって自由が丘松竹へ遊びに行ったとき(1959年〜)には、すでに事務所に置いてあったから。
1コマや4コマ、もしくは数ページの大人マンガというか、それまで少年雑誌のマンガや貸本劇画しか知らなかった私にはえらく新鮮に映った。その内容にお色気の要素が入っていたからかもしれないが(笑)。どちらかというと「漫画サンデー」の方が好みだったかな、「少年マガジン」より「少年サンデー」の愛読者だったせいもあるのか? 同じ出版社じゃないのにね。
それともう一冊、こちらは月刊だが「漫画読本」(文藝春秋)も毎月購入していた。読み物も多く、軽妙洒脱な雑誌だったと記憶している。つまりは、カズのおかげでやけにませた高校生愛読者の誕生ですね。私のマンガ好きも、つまりはカズ譲りだったのか?ひょっとしてこれらを私のために?ンな馬鹿な!
ここでひとつ、そのころの「漫画読本」をネット検索して出てくる名前を列挙してみると…秋好馨、井崎一夫、出光永、おおば比呂司、岡部冬彦、小川哲男、荻原賢次、改田昌直、加藤芳郎、金親堅太郎、工藤恒美、倉金章介、久里洋二、小島功、小林治雄、近藤日出造、境田昭造、坂みのる、佐川美代太郎、サトウ・サンペイ、佐藤六郎、塩田英二郎、島田啓三、清水崑、杉浦幸雄、鈴木義司、滝谷節雄、谷内六郎、チック・ヤング(「ブロンディ」)、チャールズ・アダムス(「幽霊一家」)、長新太、佃公彦、富永一朗、那須良輔、西川辰美、根本進、馬場のぼる、松下井知夫、真鍋博、水野良太郎、六浦光雄、森哲郎、ボブ・バトル(「意地悪爺さん」)、横山泰三、横山隆一、八島一夫、柳原良平、レイモン・ペイネ(「恋人たち」)、和田義三…どうです、懐かしい名前ばかりですね(いまだ現役でご活躍の方もおられます)。そして、併せて連載マンガのタイトルをも思い出される方も多いことでしょう。「轟先生」「ベビー・ギャング」「オンボロ人生」「あんみつ姫」「ユメコさん」「アトミックのおぼん」「おとらさん」「フクちゃん」…おっと、ずいぶんと行数を稼いでしまったが、ご容赦!
手塚治虫や石森章太郎なども執筆していますが、それはもう少し後のことですね。この「漫画読本」、現在の古書相場は2000円前後です。「漫画サンデー」は1000円位。今度、古本市などで探してみようかな。当時の定価は覚えてないけど…この十分の一くらいだったのかも(買ってたのはカズだから・笑)。
ところで、小島功描くところの女性には、高校生の私も爽やかなお色気を感じていました。「週刊アサヒ芸能」連載の「仙人部落」が深夜のアニメになったのは1963年秋、私が高校2年の時で、こっそりとでもないけど、毎週欠かさず観ていましたっけ。
この大人向けアニメ「仙人部落」、当然モノクロ作品だけど、虫プロ「鉄腕アトム」(1963年1月〜)に次いで国産二番手のアニメだったのですよ。番組企画者も凄いところに目を付けましたね(笑)。このすぐ後「鉄人28号」(TCJ)「8マン」(TBS)「狼少年ケン」(東映動画)と、バタバタと競うように放送開始となります。
この「仙人部落」を制作していたのがTCJ、のちのエイケン。後年、長寿アニメ「サザエさん」の制作会社となるスタジオです。「鉄腕アトム」と手塚治虫しか眼中になかった私は、こういった番組は完全に観る側の意識だったのでしょう、制作している会社やスタッフに関心は無かった。ただ、小島功の女性キャラクターが色っぽい声で喋ってるのが嬉しかっただけ(笑)。
そして、それから十数年が経った或る日のこと、私が監督の「まんが偉人物語」というアニメ番組の演出打ち合わせに、Uさんという飄々とした人物が現れました。かなりのベテランとお見受けするその人こそ「仙人部落」のチーフ・ディレクターだったのです。私はラインナップから迷わず「杜甫と李白」をお願いすることにしました。だってUさん、仙人そのものみたいなお方でしたもの!
さて、三年生になったばかりの頃だ。私はその束の中に映画館のではない入場券があるのに気付く。浅草…?「浅草座」「浅草ロック座」「浅草フランス座」。そう、これはすべてストリップ劇場だぜ!確か。そろそろそっち方面にも関心が向いてくるお年頃、ピンと来ましたね(笑)。さっそく戴きです。
これらの劇場、十八歳未満は入場できない筈だけど、そんなの関係ない。この頃は私、もうパチンコ屋さんにだって平然と入っていた。学校帰りに制服のままで。なにしろ釘師カズから台の選び方と釘の見方を教わっていますからね、いつだって連戦連勝。拾った玉一個で打ち止めにしたこともあるのだ(伝説!)。でも、換金はしない。一度だけ、換金はミルクでと聞いたのでパチンコ屋の脇の交換所に持ち込んだことがあって「ミルクといっても粉ミルクだよ!これじゃダメ」と断られたことがある。何たること、私は缶入りのコンデンスミルク(練乳)と交換していたのだった。そう、イチゴなんかにかける甘〜い奴。とんだ恥をかいてしまい、以来、二度と換金には行かなかった。私が交換するのはほとんどがチョコレートとタバコだ。正直に告白する。私は十六歳から吸っていた(※26歳で断煙!)。いや、初めて吸ったのは十二歳で、祖父が吸っていたゴールデンバットだった(緑色にコウモリのパッケージ)。面白半分に試してみただけだけど。お祖父ちゃんは紙巻きタバコの他にも煙管(キセル)で刻みタバコを吸っていて、それのヤニ掃除(こよりをゆって)が幼い頃からの私のお役目だったのだ。だからタバコには妙に親近感があって…アララ、話がどんどん逸れて行く。
そう、浅草の話だった! 入場招待券をポケットに入れ休日に私服で出かける(さすがに学生服はまずいかと)。街(六区)の雰囲気は独特、「盛り場」とはこのことを言うのかと、私はその雑然とした様子にキョロキョロするばかり。が、目指すは劇場だ。すぐに場所は分かった。特に緊張もせず、券売の窓口は通らずに直接「もぎり」の元へと向かう。こういったとき、変に照れてちゃいけません、堂々の入場です(おばちゃん、いちいち確認なんかしませんて!)。
初めて入る場内は、そりゃ映画館とは大違いだった! スクリーンは無く、奥に平らな舞台があり、その真ん中から「出ベソ」と称する張り出した通路のような部分がある。客席の床はコンクリートむき出しで映画館のような傾斜は無い。椅子の数も多くはなく、やけに狭い印象だ。観客の入りは満席でもなく、閑散でもなくといった感じで、スローな曲が流れ、ステージ上で踊り子さんがピンクのスポット照明を浴びて優雅に踊っています。薄物の衣装を少しずつはだけていく「ストリップ」というものを初めて目にした私だったが、少しも興奮せず、「ふーん、こういうものなのか」と妙に冷静。何人もの踊り子さんが入れ替わりに登場するけど、どれもお決まりのパターンの繰り返しと分かるとすぐに飽きてしまった。胸は見せるけどスッポンポンにはなりません。あ、全裸!と思ったときには暗転、といった、今考えるととってもおとなしいショーだったのですね、浅草のストリップというのは(だからか・笑)。それよりもむしろ初めての経験で面白かったのは、幕間に繰り広げられるドタバタのお色気コントだった。もう内容なんか覚えてないけど、変な男たちが出てきて演じるナンセンスな寸劇が可笑しいったらない。こっちの方に軍配を上げる私だったのであります。
後で知ったことだが、こういったストリップ劇場での舞台をこなした役者の中から佐山俊二、関敬六、谷幹一、東八郎、由利徹、八波むと志、南利明、長門勇、南伸介、さらには渥美清や萩本欽一といった多くの喜劇人たちが世に出て行ったというのだから凄い!もっとも、私が出かけたこの時点では、これらの人々はとっくの昔に巣立っていた(北野武だけはこの地にまだ登場しない。だって「たけし」は私と同学年だもの・笑)。
それは映画を離れて「ボウリング」のこと。
昭和三十六年(1961年)後楽園ボウリングセンターに日本初のオートマチックマシンによるレーンが登場。それまでの倒れたピンを従業員が自らセットしなおすという、なんとものどかなシステムが終りを告げ、一気にボウリングブームの幕開けとなりました。流行りものには敏感な遊戯興行界です。都内のあちこちに次々とボウリング場が造られていきます。
カズの働くY手興行もさっそく芝白金に「白金ボウリングセンター」をオープン。このボウリング場は山手線の目黒駅から目黒通りをまっすぐ明治学院大学方面に進み、国立科学博物館附属自然教育園の並びの、現、都営三田線「白金台」駅の辺りにありました。白壁の三階(四階だったか?)建てで、レーン数はさほど多くはなかった(忘れた!)が、目玉はその最上階を都内で最初の室内アーチェリー競技場にしていたこと。これもオートマチックで、矢の刺さった的が手元まで戻ってくるというシステムです(自分で抜くのだ)。機械はボウリングと同じくブランズウィック製。カズは移って間もない「大井スズラン座」支配人からまたしても異動となり、この「白金ボウリングセンター」の支配人となったのだ。まぁ、お忙しいこと!
映画三昧、マンガ三昧で楽しい日々を送る私に、もう一つの「お遊び」が増えたのです。こりゃたまりませんって!「うわぁ、やらせて、やらせて!」となりますわな。(もちろんアーチェリーもやったけど、今ひとつ惹かれなかった・笑)。
休日には二時間、三時間待ちなんてザラという時代です。いくら支配人の倅でも順番を割り込んだり、安くやらせて貰うなんてわけにはいきません。しかし、そこは抜け道、営業時間が終ってからのレーン調整・整備の時に、息抜き?を兼ねた従業員に混じって、いくらでも好きなだけ投げさせてもらえたのです。もちろんタダ。そりゃ、毎日じゃありません。せいぜい週一くらいですが、自由が丘の家を夜に出かけて終電で帰る。カズの親バカによって当然の如く提供してくれた私のマイボール(14ポンド)、マイシューズがカズのロッカーに入っていますから、いつも手ぶらで出かけるという、お気楽高校生でした。時には同級生を引き連れて「いい顔」させてもらったり(そんなときにはなぜかカズも現れて、自分も投げたりして、「おまえの親父、いい親父じゃん!」を演ずるのです。ヤレヤレ)。私のスコアはというと、たまに200アップもして、アベレージは160くらいだったかな…(おいおい、ホントか?)。このときのボールとシューズは、硬いマイバッグに入って今も自宅の物置に在る。ほこりを被って金具は錆びて、もう骨董品みたいなモノですね。ボールの穴は自分の握りに合わせてあるし、今でも使えると思うんだけどなぁ。
このボウリングブームはしばらく続きました。日本プロボウリング協会が設立されて、ゲーム中継のTV放送が始まった昭和四十年代の数年間は絶頂だったんじゃないのかな。私も当時のスター選手の一投一投に声援を送ったものです。時にパーフェクトなるか!なんて日にゃ、自分のことのように興奮して。岩上太郎、矢島純一、西城正明、中山律子、並木恵美子、須田開代子、石井利枝、野村美枝子なんていう懐かしい名前がすぐに出てきますね(女性の方が多い・笑)。
カズの支配人業もしばらくは落ち着いて、このボウリング場に専念です。Y手興行は映画業界に通じる会社ですから、俳優や、歌手、タレント、喜劇人など、ボウリングのとりこになった芸能人がずいぶんと常連になっていました。カズはその内の幾人かとはやけに親しくしとりましたよ(ちゃん付けで・笑)。
後年、私がタツノコから虫プロに移った時に、アニメーターたちの親睦ボウリング大会(たしか「どろろ」班だ)を、この「白金ボウリングセンター」で開催させてもらった。富士見台から白金なんて、今考えるとずいぶんと遠い。いろいろ便宜を図ってくれてたんだろうけど、みんな、ありがた迷惑だったんじゃないのかなぁ(笑)。
ところで、もう一つのアーチェリー場の方はというと…目論見は見事に外れて閑古鳥。いつの間にか撤退、改装となっておりました。
しかし、辞めて手伝ったその人の仕事は、やはり満足できない。むしろ外注としての制約だらけで勉強には程遠い。さらには入社が叶わなかった東映動画スタジオの作品(「海賊王子」)という皮肉だったのであります。
そこに声を掛けてきたのが坂口尚三という男。彼は或るマンガ同人誌を介して知り合った高校時代からの友人で、高校在学中に一足早くこの業界に身を置いていた。しかも、私の憧れの虫プロに!(入社すぐに高校を中退している)。私はそれを知っていたが、以前「オレは卒業後は東映動画に入るからさ」なんて言っていた手前、バツが悪くて近付かなかった(笑)。「だったら一度、虫プロに遊びにおいでよ」「わかった」
そして訪ねた虫プロ。するとそこには私のための実技試験が用意されていた。「え?」言われるままにレオを描く。当時、「ジャングル大帝」班に坂口はいた。しかも原画の中心スタッフとして。私に声を掛けたのは彼の意思なのか?制作の人間に「誰か知らないか」とでも言われてのことか、それは知らない。虫プロも業務拡大により人材を求めていたのだろう。拍子抜けするほど簡単に私は採用された。しかも給与は経験者としての扱い。三月からの入社で配属先は「ジャングル大帝」勝井千賀雄演出/坂口原画班の動画。なんということ!高校時代の友人が私の直属の上司となったのだ。しかもこれからは仕事を教えてもらう立場。参ったなぁ(笑)。でも、坂口の上手さは群を抜いていた。手塚治虫をして「あの人は天才です」と言わしめたという。ここは彼を信じて付いていこう。遠回りしたけど、夢の虫プロの一員になれたことに感謝だ。
もうこのころはいちいちカズに報告などしない。まぁ、虫プロに入ったよ、くらいのことは伝えたと思うが、私は祖母との暮らしが全てに優先だ。通勤もグッと近くなったし、給料も上がった。仕事も楽しい。毎日が充実していた。
虫プロに入った年の十一月、私は二十才になった。仕事は途中で社内の編成替えがあり、坂口班全体は「鉄腕アトム」に移動となって放送終了までの番組テコ入れにあたった。そして次の作品が「リボンの騎士」と決まり、番組のスタートに合わせ、新たに二名の原画を動画スタッフの中から昇格させることになった。原画マンたちの内部投票によってそれは決まる。私はその内の一人に選ばれた(坂口の後押しに違いない!)。これには辞退するわけにはいかない。こうして、坂口は演出に、私は原画になった。(このときのもう一人が第二原画だった、今ローマに暮らすW辺Y子・余談)。
さて、カズが珍しくも成人の祝いをくれると言う。「何でも欲しいものを言え」と言うので、私は絶妙のタイミングとばかり、「じゃあ、ストップウォッチをお願い」「ん?」演出家はもちろんだが、原画マンにストップウォッチは必需品だ。動きのタイミングを計ったり、台詞の長さを確かめる。1秒を24コマに区切った撮影シートにセルの番号を記入する際も、常に片手に握り締めたストップウォッチを見ながらの作業です。会社から貸与されることにはなるのだが、中には個人所有もチラホラ。
当時のストップウォッチの値段はそりゃ高かった。新卒の給料が二万前後のころだったが、セイコーの十分の一秒計が一万円!それをねだった私に、カズは応えてくれました。嬉しかったなぁ。ピカピカのストップウォッチを手にして、いっぱしの原画マンになった気分。最高だぜ! ただ、このストップウォッチ、使用頻度の激しさに耐えかねてしばしば針が折れちゃうんだよねぇ。修理費もバカ高かった(それは私負担・トホホ)。
<第4回>
上京当時、父と一緒に暮らした記憶が殆んど無いと前号に書いたが、それも道理で、再婚していたカズは西武池袋線の線路を挟んだだけの、すぐ近くの
と、いうことで、椎名町の家は田舎から出てくる私たち三人のためだけに用意されていたというわけなのだ。田舎の両親は前もってカズ宛に、東京で暮らすための家の購入資金を送っていた。「もう少し広い家が用意されていると思ったんだけどねぇ」と、後年祖母がこぼしていたから、その辺は遊び人のカズがおそらく…ね(笑)。すっかり忘れていたことが、こうやって記憶を手繰りながら書いていると、何かの拍子に突然、「あ、そうだった!」なんて思い出してくるものです。今回書くのも、そんな思い出話の一つだ。
昭和28年(1953年)の4月(「並木座」開館の半年前)、くりくり坊主頭の田舎の子供そのまんまの私は
ひょっとしたら東京でこうやって探した末に「やっぱり地元の子を使おう」となったのかしら?それだったら面白いけどね。「ならば、俺の子供はどうだ?」とかなんとか言ったんだろうなぁ、お調子者のカズは(笑)。上手くいきゃステージパパとなって左団扇に…「おい、もっと働くんだ!」なんて、「角兵衛獅子」かよ、オイ。
いずれにしろ、おじいちゃん子、おばあちゃん子で「内弁慶」の私が、人前でお芝居なんか出来るわけがありません。「絶対にヤだ!」と言っていたそうですよ。もっとも「カメラ映り」がどうだったのかは不明ですから、断る以前に不合格だったのかもしれませんがね(笑)。ただ、自分で言うのもなんだけど、お目目パッチリのけっこう可愛い子供だったのですよ、この頃は。え?今となれば惜しかったかって?いやいや、ろくな結末を迎えてないでしょうね。だいたいが子役は大成しないものです(失礼)。寿司屋チェーンのオーナーになった人もいたけど、犯罪に手を染めた輩もいたような…(余談)。
☆総本舗に
☆並木座こぼればなし
http://d.hatena.ne.jp/manga-do/20051215
http://d.hatena.ne.jp/manga-do/20051217
http://d.hatena.ne.jp/manga-do/20060217
http://d.hatena.ne.jp/manga-do/20060218
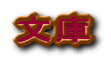
この幼い当時で私が鮮明に覚えているのは、並木座ではない銀座のもっと大きな劇場(どこかは不明。日劇とかテアトル銀座とか言えればいいのでしょうがねぇ…)に「ダンボ」を観に行ったときのこと。劇場の周りの行列と間近で見るスクリーンの大きさに驚いたっけ。このとき一緒だったのは父ではなく祖父だったような気がするな。サーカスのテントの中、ダンボが空中を飛ぶシーンが脳裏に焼きついています。併映は「こぐまのボンゴ」。この一輪車乗りのシーンも懐かしい。ネット検索してみたら、この「ダンボ」の日本公開は1954年3月ですって。やはり私が一年生の終わりの時だ。アメリカでは1941年(「ボンゴ」の方は1947年)です。
☆総本舗に
(ふみくら)
私が高校入学と共に同居することになったためではないだろうが、同居してすぐにカズは職住至近の「自由が丘松竹劇場」から別の映画館に異動となった。そこは「大井スズラン座」というY興行が経営する三つ目の映画館。立場は同じ劇場支配人です。封切館だったのか、二番、三番館だったのか、名画座だったのか、洋画系だったのか、そこらは一切不明(覚えてない・笑)。東急
なにしろカズときたら私が学校に行くときには寝てるし、夜は私が起きてる時間にゃまず帰ってこない。父子の会話の実現は、私がカズの仕事場に押しかけないと難しいのですよ。このときも何かの相談事があってのことだったんじゃないのかな。
十数年経ってから、改めて一つ屋根の下に暮らすという父と息子の関係は、どこかお互いぎごちなく、私としても素直に「おとうさん」なんて口に出せないのですよ。「ねぇ…」とか「あのさぁ…」とかでごまかしちゃう。カズはその辺は無頓着を装ってるのか、強がってるのか、負い目を感じてるくせに、いつだって「俺は親父なんだ!」って偉そうに振舞ってた。倅のためなら俺はいくらでも力になってやるぞ!というような。
高校一年の夏休み明けにこんなことがあった。私はその夏休みを全て使って全72ページのマンガを描いたことがあるのだが、それを講談社と光文社に持ち込んで、編集の人に見てもらって、意見を聞いて、もう私はそれで大満足。終ったことだった。ところが、カズは「その原稿を俺に預けろ」と言うのですね。「貸本業者を知ってるから見せる」と。そんなぁ…中身は火星を舞台のSF漫画だし、そんな目的で描いたんじゃないよ! と言っても無駄なこと。ある日、
カズの空回りは私が三年のときにさらに発揮されます。私が「進学はせずにアニメーターになりたいのだ」と告げると、「だったら俺に任せろ」「え、どういうこと?」「俺が東映に頼んでやる」また始まった(笑)。もっとも、当時どうやったらアニメーターになれるのかなんて、具体的には何も分からなかった私です。希望する虫プロダクションの求人情況は知らないし、「西遊記」や「少年猿飛佐助」の劇場用漫画映画で承知の東映動画に入社できるならそれは願ってもないこと、カズは一応映画業界の人間、何らかのコネがあっても不思議はないのかな…なんてことで、とりあえずは「じゃ、お願いします」と。そしたら、ホントに東映の人にコンタクトしたらしく、「大丈夫だとさ。研修後の初任給は3万だ」「エエ〜ッ!」いやぁあのときゃ驚いた。高卒の初任給が1万数千円の時代です。アニメーターって凄い。私もすっかり有頂天。ところが、これがとんだぬか喜びでした。
カズが頼んだ人は東映は東映でも東映本社のエライさん。肝心の東映動画ではなかった。しかし、その人も安請け合いをしたものですな。専門的な技術、才能が要求される仕事にコネ入社など有り得ませんて。しかも東映動画は例年行っていた定期採用を前年限りで打ち切り、新規採用は中止となっていたのです。で、どうなったか? その東映のエライ人の計らいで特別に採用試験を受けることになったのですよ。
ここは私の文章を収蔵する「文庫(ふみくら)」です。あちこちで書き散らしたものをとりあえず転記しておくことにしました。はるか昔の、ほろ苦い思い出の「自作詩」などもそのうちに…載せるかも?
その青春残滓は…
●「並木座ウィークリーと共に」マイ・オールド・シネマ・パラダイス(月刊「広場」連載中)
カズの結婚が〈いとこ同士〉ということにショックを受けた私だったが、実は、母はSおじさんとは血縁が無かったのだ。母の説明から、おじさんのお嫁さんの連れ子だったと判明。「私も本当の父親は知らないのよ。Sさんがお父さんだとして育てられたの」何ということでしょう! 母も私と同じような境遇に育っていたとは…。
でも、これでカズと母との血縁不存在にホッとした私です。いとこ同士なのに会ったことも無いという不可解さもどうやら納得できました。祖父兄弟四人は長男だけが本家を継ぎ、他の三人はそれぞれ他家に婿入りしていたのです。次男坊の祖父は樋口家に、三男坊のSおじさんはF家にと。同じ山梨県内でも婿入り先はお互いに遠く離れていました。
私を残して実家に戻った母は、やはり出戻りは辛いのか、そのころ東京に暮らしていた叔母を頼って上京します。そして就職した職場で、ある人に見初められ結婚。相手は、母が離婚経験も子供を産んだことも承知の上でのことだったといいます。そして、二人の間に子供は女の子ばかり三人。「あなたを置いて去ったからかしら、男の子は出来なかったわ」いやぁビックリ!カズには二人、母には三人、妹ばかりが五人だぁ〜〜ッ!
やがて、その旦那さんは職場から独立し、○○鋼業という自分の会社を興します。母は幸せでした。経営も順調で「おまえが残してきた男の子、もし苦労しているなら援助してあげたい」とまで言っていたとか。そう、過去形。私と会う前年、旦那さんは急逝したのです。私と会った時の母はすでに未亡人になっていたのでした。まだ三十九才(私を産んだのは二十一才)です。そして、夫の形見でもある○○鋼業の経営を引き継ぎ、なんと女社長という立場になっていました。妻から突然に経営者、私などよりはるかに数奇な運命に翻弄されている母、凄い人とめぐり会ってしまいましたねぇ、この私。カズは柔らかい興行、母は堅い鋼業、ホント対極だな(ふざけてる場合か!)。
母の経営する会社は東急東横線の元住吉にありました(なんと、自由が丘からすぐではありませんか!)。自宅も広く、日吉の慶応大学の学生たちを下宿させるなどしていた。虫プロ時代、幾たびか泊まりに行ってその学生たちとジャン卓を囲んだっけ(もちろんカモる・余談)。その学生の一人が長妹とのちに結婚(さらに余談)。
余談ついでに言うと、経営に陰りが出る以前の最盛期の虫プロで、川崎市の生田あたりに移転するという話があった。大きなスタジオを建てて、社員全体が移動となる大プロジェクト。この話に私は母との暮らしが瞬間頭をよぎる。「だったら、すぐ近くじゃないのよ!」母も期待していた。私は唯一の男の子、いずれヤクザな商売はやめさせて転職を… が、そうはいきません(笑)。虫プロはアレヨアレヨという間に傾き始めます。毎年100人単位で増えていた社員が、今度は100人単位で去っていく。移転話はつかの間の幻に終りました。
母は高校生の長女から小学生の末っ子までの三人の妹たちに、私を「親戚のお兄ちゃん」と紹介しました。しかし、突然現れた親戚のお兄ちゃんというのも、どこか不自然ですよね(笑)。それぞれには嫁ぐ前に打ち明けたと言いますから、かなりの長期間それで押し通していたことになります。母としてはなかなか辛かったことでしょう。私も入り浸るようなことはせず、極力距離を置くこととしました。お互いの存在を認め合ったことで、一つの解決を見たのですから。
さて、こうして母と私が会ったことは、カズにも知れることとなった。でも、どうだったとか、今何をしているとか、一切聞こうとしない。ここからがカズの凄いところなのだが、以来全ての親戚がらみの冠婚葬祭への出席が私の役目となったのだ。
何かあると「おい、おまえ、行っといてくれ」の一言です。どんなときでも「カズの名代で来ました」と。もう全てがオープンになったんだという安心感なのでしょうかねぇ、カズにとっては。親戚も私の生い立ちを知っていますから、「おまえも大変だねぇ」といつだって声を掛けてくれる(笑)。私はカズの子供なのか、はたまた私がカズなのか、まさにカズだ、雅一だ(ふざけ過ぎ!)。もう、なんだか訳が判らない立場であります。
<第24回>
カズは故郷に家を建てるという。しかし、その場所はかつて自分が生まれ育った場所ではない。若き日に、親に全てを捨てさせているのだから、本来、故郷に戻る場所など在るはずはないのだ。そこは…再婚した同郷の女性が親から相続した土地だった。おいおい、嫁さんの土地にかい?「でも、うわモノは俺が建てるんだ!」って…うーん、どこまで「甘ったれ」なんだ!(ま、いいけどね・呆)。
畑を宅地に転用したその土地に、自身の基本設計による新居が完成すると、退職が待ち遠しくてたまらない様子のカズ。一日も早くのんびりと隠遁生活に入りたいとまでのたまう。ちょっとちょっと、あんた東京で一旗上げるんじゃなかったのかい? 自分の限界を見切ったということなのか? やるだけやったからもういいってのかい? 結局のところ、好きな興行界でそれなりに仕事はしたかもしれないが、個人として東京の地に何を遺した? 椎名町の家は不要だから処分するというし…面と向かっては言えないが、正直、情けないやら口惜しいやら…自ら望んで上京したわけではなかった筈の、亡くなった祖父母のことを想うとね。
「おーい!東京へ出て行ったカズさんが、嫁さんの実家に戻ってきたぞォ〜ッ!」
きっと、幼なじみの連中はそんな声を上げることでしょう。
福島から戻ったカズは、並木座時代からの盟友で上司のSさんと共に、池袋にある結婚式場「T方会館」の専務と常務になっていた。アレ、いつの間にY興行を離れたのでしょう? それとも両社に何かつながりがあるのかな、事情は分かりません…というより、もう私はそんなことはどうでもいいと(笑)。
私が、所帯を持ってから数年が経ち、子供も生まれて生活に追われていた三十代半ば、カズは還暦を迎えようとしていた。カズと私はちょうど二周りの年齢差です(同じ戌年)。カズの口から「還暦を期して田舎に帰る!」との宣言が出されました。役員だし、会社が定年を決めているわけでもないのだから辞めることはない、という周囲の慰留にも耳を貸さずに。
そして、ある日のこと、私の家にやってきたカズは
「おい、還暦の祝いは8ミリだ」
「え?」
「8ミリの撮影機が欲しい」
「…買ってくれってこと?」
「当たり前だろ」
映像の世界もそろそろビデオが主体になるのでは…という頃です(ビデオ撮影機の個人への普及はも少し先)。私は内心(今さら8ミリかなぁ…)ではあったものの、映写技師が隠遁後の趣味を〈フィルムでの映画撮影〉に充てる、これもカズにとってはごく自然な流れなのか、と納得。それと、自分で買うことだって出来るだろうに「俺の祝いにと、子供が買ってくれたんだ」という大義が必要なのですよね、カズとしては。いいでしょう!きっと、可愛い孫の姿でも撮ってくれることだろうし。
「分かったよ」
「そうか、じゃ映写機とセットで頼んだぞ」
「…?…」
「映写機が無きゃ、映せんだろうが」
「…ハイハイ!」
独りの負担もシャク(笑)なので、妹二人にこの要望を伝えて幾らか出させ、生フィルムも添えてプレゼントしたのでした。
本当にスパッと、60歳になって即、退職したカズは椎名町から去った。しかし、何の未練も無いんですねぇ…(悲)。子供時代の私が祖父母と三人で暮らした、思い出がたくさん詰まった家は、隣家が購入してすぐに取り壊され、隣家の増築部分へと変貌してしまったのであります。感傷に浸る余裕もなく、それこそ、あっという間の出来事でした。
さて、故郷の新居で老後?の暮らしを始めたカズ。一体どんな暮らしぶりなのでしょうか?(あ、娘たちはすでに嫁いでいるので、夫婦二人だけの暮らしです)。何もせずにブラブラ過ごすだけの日々? まさか、60歳でそれは無いでしょうよ。趣味で始めた筈の「8ミリ」のその後も気になりますねぇ。
この連載、次回が最終回となります。どう締めくくるのか、うーん、悩ましい……
<第12回>
軌道修正して、今回はカズの思い出ばなしをば……
カズは無類の競馬好き。まぁ、天衣無縫な「遊び人」だから何かのギャンブルに夢中となるのは至極当然のことなのでしょうが…パチンコや麻雀、競輪、オートレース、競艇など、他の賭け事には全く興味なし。ひたすら競馬、競馬、競馬!
私がカズに連れられて初めて競馬場(府中・東京競馬場)へ行ったのは1955年(小三)の秋の天皇賞だった。青い空に、広がる芝と散乱する馬券、そして勝ったダイナナホウシュウという馬名はしっかり記憶に刷り込まれている。後年、競馬予想の新聞を買いに走らされたこともあったし、日曜日に渋谷や新宿の場外馬券売り場に連れて行かれたこともあった。私は何が面白いのかさっぱり分からず、今に至るも他人?に賭けるギャンブルには興味がなく、馬券・車券・舟券を買うことも無い(反面教師となったのなら感謝・笑)。しかし、子供時代に、父親とたまに出かけた記憶が競馬がらみしかないとは…なんともトホホでありますな。
さて、「自由が丘松竹映画劇場」の支配人となった自由が丘で、カズの競馬好きにさらに拍車がかかった。原因の大きなものは、「自由が丘松竹」のお隣の東宝映画の封切館「南風座」の経営者、T塚さんにありました。Tさんは、ダービー馬アサデンコウ、天皇賞馬アサホコの馬主でもあり、当時の日本馬主協会会長でもあります。人の懐に入り込むのが特技のカズはすぐに懇意に(笑)。このTさん、昔は役者だったようで、ネットで調べたところ、新興キネマとか帝国キネマに出演の記録があります。「南地囃子」「暴風警報」というその出演作から「南風座」という映画館名が付けられていたのだと、今になって判明。面白い!
カズはそのTさんからいろいろ便宜を図ってもらっていたのでしょう。競馬場ではいつも馬主招待席に入り込んでいたし、入手が困難といわれた個人電話投票の権利もいつの間にか取得していた。(この権利は、仕事から引退して田舎に隠遁するようになった際に大いに活用していたっけ。亡くなったとき、この権利の返還手続きは私がやった。※余談)私から見ると、他所の社長さんといつも仲良くつるんでいるカズが不思議でしょうがなかった。きっと、二人で映画談義じゃなく競馬談義をしていたのでしょうねぇ。まぁ、おかげで私も東宝映画はずいぶんと見させていただいた。黒沢明の「用心棒」「椿三十郎」「天国と地獄」は、高校時代に全てこの「南風座」で見たのです。顔パスでなく、ちゃんと招待券で(笑)。
しかし、カズも仕事はしていましたよ。劇場の上映プログラム作りもそのひとつ。「並木座ウィークリー」のプログラムは当時の支配人Sさんの編集でしたが、おそらくカズもそのお手伝いをしていたのでしょうね、手馴れた様子で「自由が丘松竹劇場」の毎週のプログラムを作っていました。松竹本社から届く宣伝パンフレットからスタッフ・キャスト・解説の部分などを切り抜いたり、プログラムに載せる写真の選定、近所の商店などからの広告作り、自分で構成から編集までをと、糊とハサミを器用に扱って、版下を制作するのです。私もそれを面白く眺めていました。
私が中学校時代に劇画クラブの同人誌の編集・製本・発行などを一人でコツコツとやれたのも、そんなカズの器用さをどこかで受け継いでいたのでしょうね。
この上映プログラムや、当時の劇場のロビーや道に面したショーウィンドウ内に貼られた「只今上映中」「次週上映」の映画場面の数々は、きっと今でも田舎の家のどこかに埋もれているのだと思うのです。事実、桑野みゆき、川津裕介の「青春残酷物語」(昭和35年/監督・大島渚)の映画のシーンのいくつかを田舎で見せてもらい、「おやじさん、こんなものまで持ってたの!」と驚いた記憶がある。そのとき、他の映画の写真も見たと思うし、いつか本腰据えて捜してみましょうかね。
西武池袋線
試験内容は(おぼろげな記憶では)陸上のトラックを走る男の、四地点での走行ポーズ(前・後・横位置)と、体操選手の鉄棒からの着地。一枚の枯葉の舞い落ちる様子を描く、というもの。作文もあったっけ。一応、適正を見るには理に適っていますね。私は自信満々「楽勝モノ」で完了です。
が、結果は全員不合格でした。「息子さんを採用するつもりだったが、適正が無いなら仕方がない」というのが仲介者の言。カズの弁明は、つまりは試験の実施自体が最初から「新規採用はしない」という結論に合わせたものだった。つまり「義理立てのための試験」だったと(だからあきらめろ)と言わんばかり。しかし、これが真実かどうかは、今となればいささか怪しい。本当に見込みが有る人材であれば、「飛込み」だって採用するだろうと思うのですよ。当時の私にそれだけの資質は無かったということなのでしょう。原則を変えさせるだけのね(そして、昭和39年10月16日付の不採用通知が手元に残る。これ、近年カズの遺品の中に発見・笑)。
拝啓 秋寒の侯、益々御健勝のことと存じます。扨、貴殿当社御志望につき過日実技試験を実施いたしましたが其の結果折角の御志望ではございましたが誠に残念ながら貴意に添え兼ねることとなりましたので何卒御諒承下さい。以上御通知致します。
敬具 東映動画株式会社 勤労課(原文ママ)
私の中では、カズを責める気持ちは起きません。「まぁ、そんなに上手くいくわけはないよな」と。ただ、困ったのは、「進学はしない。就職は自分で決める」と先生に言ってしまった手前、このままだと就職浪人になってしまうなぁということ。なにしろ世間知らずだから、求人のある会社でないと就職できないって思い込んでいた。問い合わせることも思いつかない。だから、「虫プロはどうして求人が無いのかなぁ…」って、それだけ。求人情報に気付かなかったのかもしれないけど(笑)。
さて、就職コースの女生徒たちは続々入社が決まります。我が道を行くとばかりに泰然自若を気取る私でしたが、「アニメやマンガは夢の世界として、サラリーマンになるのが現実的なのかも」と、某有名企業の「追加採用若干名」という求人を見つけ、それに応募したのです。全くカズには相談せず、私の独断で。卒業後は椎名町に戻って祖母と暮らす決断をしていたから、就職することだけは何としても叶えないといけません!
筆記試験は無事通過。最終の役員面接にこぎつけました。ここを通れば採用が決まります。さすがにドキドキ…。ところが、この役員面接の場で、とんでもないことが起きたのです。「君の志望動機を聞かせて」という質問に、「宣伝部に入りたいから」「え?一般事務職の求人だよ」「分かってますが、宣伝部で働きたいのです」この期に及んでも絵を描く仕事につなげたいと思ってたんでしょうね、私って。(こいつはダメだ!)と判断したのか、一人の役員が口を挟みます。「ねぇ、君」「はい」
「君は母親が違うんだねぇ…」「はぁ?…(この人何言ってるの)どういうことですか?」その役員は私関連の書類を眺めながら、「だって、戸籍には違う名前が書いてあるよ」「(戸籍なんてこれまで一度も見たこと無かった)…そんなことは…」「知らなかったのかい」「…?(頭ン中、真っ白)?…」そこから先の記憶無く、役員面接が失敗に終ったことは確かです。母親が違う…って、ンなバカなこと……じゃ、私を産んだのは誰なのさ?