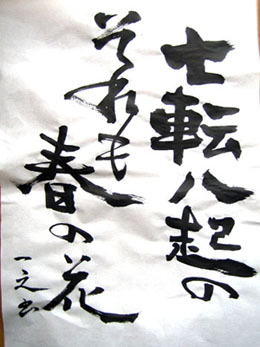| 時はいつでも誰にでも同じリズムで流れている。 でも、集中力は時間を変える。 昔、野球の神様といわれた人が「ボールが止まって見える」と言ったそうだが、今でもイチローがボールにバットを当てる瞬間は違う時間が流れているような気がする。鍛錬した空手家が相手の技の隙を突く時も同じだ。ただ勘で動いているのではなく、そこには集中した稽古から培った「確信」があるのだ。例えば相手が蹴りを放つ瞬間(→当たる箇所を予測する→受けるか合わせるか選択する→合わせることにする→相手の攻撃が終わった瞬間の態勢を読み、急所に照準を合わせる→出す技を選択する→技を出す)ここまでをほぼ一瞬で行うわけだ。結果、一本勝ちとなったりする。これが技の醍醐味である。 文字にするととてつもないが、人間は凄いのである。 寒い季節の稽古は身が引き締まり、稽古の集中力も増す。冬の稽古はやったあとが暖かい。着替えてしばらくは体がポカポカと火照っている。無我夢中でやった稽古は「あっ」とう間に終わるけど、肉体に確実に刻まれ、心に長く残る。「千里の道も一歩から」というとなんだか果てしないが、上達する実感、強くなる実感は楽しいものだ。ひとつひとつ良い稽古を重ねよう。
|